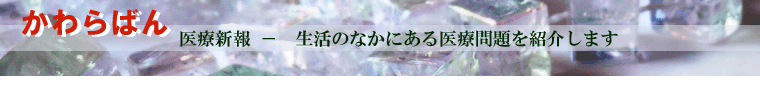|
| ペインクリニックの基礎・臨床・応用の3分野構成を企画し、会長をつとめた南敏明教授 |
| 成果を挙げた3分野構成の特別講演 |
まず、ペインクリニックの基礎分野から「痛みの発生維持機構と鎮痛薬の作用点」と題して伊藤誠二氏(関西医科大学副学長・医化学講座教授)が講演した。 伊藤氏は、いわゆる急性痛は生体に対する一時的な警告反応であって記憶には残らないようになっているが、慢性痛は脊髄における痛みの記憶であると指摘し、 末梢組織からの持続的な痛み刺激の入力が脊髄後角での二次ニューロンの興奮性変化を引き起こすメカニズムなどを紹介した。
次に、臨床分野からは「緩和医療の全人的疼痛―スピリチュアルペインをどうするか」と題して畑埜義雄氏(和歌山県立医科大学付属病院長)が、がん終末期 医療の現場で誰がどのように患者のスピリチュアルケアをすべきかについて言及した。
そして応用分野からは田中紀之氏(大和ハウス工業・総合技術研究所フロンティア技術研究センター ライフサポート研究グループ住居医学研究チーム)が、 「住み慣れた地域で住み続けるために―Aging in Place に向けた住環境」と題して、講演をおこなった。田中氏によれば、人は高齢化に伴って「居を移すこと」に 対する適応力も弱くなる。自宅での介護が難しくなれば施設に移り、疾病の管理が必要になれば病院に移らざるを得ないといった現代の高齢者の居住環境の変化が、 認知能力の衰退した高齢者に与える影響なども考慮していく必要があると、その研究の一端を紹介した。